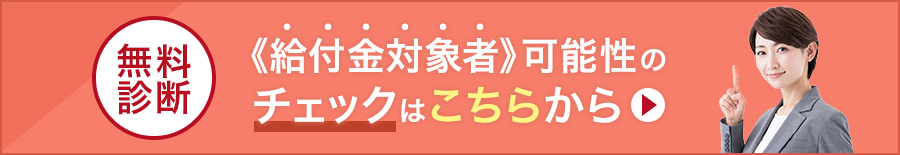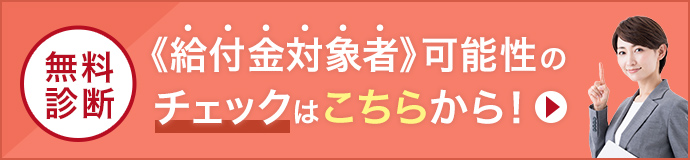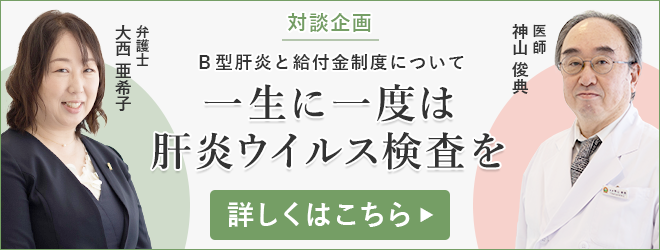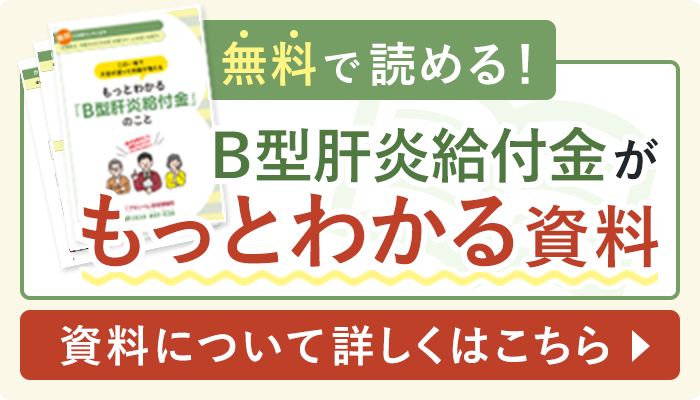監修者情報

- 資格
- 弁護士,行政書士(未登録),肝炎医療コーディネーター※
※地域により名称が異なります。
B型肝炎の給付金を受け取るための要件
B型肝炎の給付金は、幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方やそのご遺族の方が受け取れる可能性のあるお金です。
受給対象者の方は、国に対してB型肝炎訴訟を起こし和解することで、給付金を受け取れます。
ただし、国と和解し給付金を受け取るためには一定の要件を満たさなければなりません。対象者ごとに定められた要件は、以下のとおりです。
B型肝炎給付金の対象者別の受給要件
| 受給対象者 | 受給要件 |
|---|---|
| 一次感染者 |
|
| 二次感染者 (母子感染者) |
|
| 二次感染者 (父子感染者) |
|
| 三次感染者 |
|
なお、これらの要件を満たす受給対象者ご本人が亡くなっている場合には、ご遺族の方が給付金を請求できます。
B型肝炎の給付金をもらえない人の具体例
「B型肝炎の給付金を受け取るための要件」で紹介した受給要件に”当てはまらない”方は、B型肝炎の給付金を受け取ることができません。
具体的には、以下のような方です。
- 感染原因が集団予防接種等ではない方
- 持続感染をしていない方
- 昭和16年7月1日以前または昭和63年1月28日以降に生まれた方
- 満7歳を迎えてから初めて集団予防接種等を受けた方
- ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している方
- 証拠となる資料がない方
それぞれ詳しく見ていきましょう。
感染原因が集団予防接種等ではない方
給付金を受け取れるのは、満7歳になるまでに受けた集団予防接種等(集団予防接種および、ツベルクリン反応検査)における注射器の使い回しにより、B型肝炎ウイルスに感染された方です。
そのため、たとえば以下のような原因でB型肝炎ウイルスに感染したと判断された場合、給付金を受け取ることはできません。
- 性交渉
- 輸血・臓器移植
- 刺青・ピアスの穴あけ
- 剃刀などの使い回し
- 昭和16年7月1日以前生まれの母親や父親からの母子感染や父子感染※ など
ただし、これらの原因に心当たりがある場合でも、医療記録(カルテ)や血液検査などで感染原因を調べていくと、幼少期の集団予防接種等が原因だとされることも多々あります。
そのため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
※昭和16年7月1日以降生まれの母親や父親からの母子感染や父子感染の方は給付金の受給対象となる可能性があります。詳しくは母子感染でもB型肝炎給付金を受け取れる?要件や給付金額は?弁護士が解説をご覧ください。
持続感染をしていない方

B型肝炎ウイルスの感染には、一時的に感染したあと免疫機能によりウイルスが体外へ排出される一過性の感染と、長期間継続して感染した状態を維持する持続感染の2つがあります。
そして給付金の受給対象者は、B型肝炎ウイルスに持続感染している方のみで、一過性の感染の方は、給付金を受け取ることができません。
持続感染であることが認められるのは、以下のいずれかのケースです。
B型肝炎ウイルスの持続感染について検査を受けられる医療機関の一部は、以下のページで紹介しています。
昭和16年7月1日以前または昭和63年1月28日以降に生まれた方
集団予防接種等によるB型肝炎の感染について国が責任を認めている期間は、予防接種法が施行された昭和23年7月1日から、国が注射筒を1人ごとに取り替えるよう指導した昭和63年1月27日までです。
そのため、昭和16年7月1日以前または昭和63年1月28日以降に生まれた方は、一次感染者としてB型肝炎給付金の対象になりません。
ただし、昭和63年1月28日以降に生まれた方は、二次感染者、三次感染者の要件を満たせば、給付金を受け取れる可能性があります。
満7歳を迎えてから初めて集団予防接種等を受けた方
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれ、集団予防接種等を受けた方であっても、満7歳を迎えてから初めて集団予防接種等を受けた場合には、一次感染者として給付金を受け取ることはできません。
これは、免疫機能が未発達な6歳までの間にB型肝炎ウイルスに感染しなければ、原則として持続感染しないとされているためです。
ただし、二次感染者、三次感染者の要件を満たせば、給付金を受け取れる可能性があります。
ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している方
B型肝炎ウイルスには、ジェノタイプAやジェノタイプBという遺伝子型(ジェノタイプ・ゲノタイプ)の種類がいくつか存在します。
さらにジェノタイプAには、ジェノタイプAaとジェノタイプAeがあり、ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している方は、給付金を受け取ることができません。
これは、ジェノタイプAeは平成8年以降に日本で感染が確認された遺伝子型であり、満7歳以降の感染であっても持続感染化することがあるためです。
集団予防接種等で注射器の使い回しが問題となった昭和23年から昭和63年には感染が確認されておらず、成人後感染により持続感染した可能性があることから、手続の対象外とされています。
証拠となる資料がない方
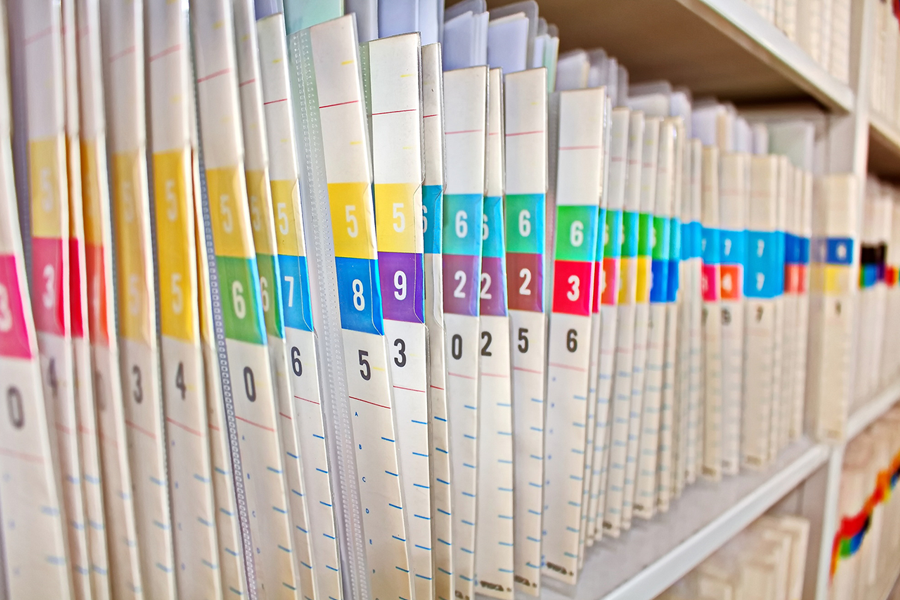
B型肝炎給付金を受け取るためには、感染経路や病態を証明するための資料を提出し、国に対して訴訟を提起しなければなりません。
しかし、保管期限が過ぎた医療記録(カルテ)などは廃棄されてしまっているケースもあります。
証拠となる資料がない場合、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染したことを証明できず、給付金を受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。
ただし、ご状況によっては代わりとなる資料を提出することで、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染したことを証明できる可能性もあります。
そのため、「資料がない・見つからない」、「資料の集め方がわからない」というだけですぐに諦める必要はありません。
まずは、B型肝炎の給付金請求に詳しい弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
B型肝炎の給付金をもらえないと誤解されやすいケース
B型肝炎の給付金を受け取れないケースがある一方で、「給付金をもらえない」と誤解されやすいものの、実は給付金を受け取れる可能性のあるケースもあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
二次感染・三次感染でB型肝炎ウイルスに感染した方
一次感染の方だけでなく、一次感染の方から母子感染・父子感染された二次感染の方や、二次感染の方から母子感染・父子感染された三次感染の方も給付金を受け取れる可能性があります。
なかでも、特に多い母子感染による二次感染の方が給付金を受け取るための要件は、以下のページで解説しているため、参考にしてみてください。
無症候性キャリアの方
無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスに感染しているものの、症状が出ていない状態です。
症状が出ていない無症候性キャリアの方も、要件を満たしていればB型肝炎給付金を受け取れます。
感染から20年経過した場合の無症候性キャリアで和解すると、給付金だけでなく、受給者証(特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証)を受け取ることが可能です。
そして、受給者証を提示すれば、B型肝炎ウイルスや肝機能に関する血液検査や肝疾患予防のための超音波検査などを自己負担なく受けられるようになります。
受給者証を利用して定期的に検査を受けることで、万が一症状が出てしまったときも早期発見でき、重症化のリスクも下げられるでしょう。
B型肝炎ウイルスに感染した方のご遺族の方
B型肝炎ウイルスに感染されたご本人がすでに亡くなられている場合、ご遺族の方が訴訟を起こすことで、給付金を受け取れる可能性があります。
ただし、ご遺族の方が給付金請求を行う場合、残された資料のみで手続をしなければなりません。
ご本人が請求する場合とは異なる点もありますので、弁護士に相談したほうがスムーズに進められるでしょう。
「B型肝炎の給付金がもらえないかも?」と判断に迷ったら弁護士へ
なかには、「自分がB型肝炎の給付金を受け取れるのかわからない」という方もいらっしゃると思います。
しかし、よくわからないまま「給付金をもらえない」と決めつけてしまうと、本来は受け取れるはずだった給付金を受け取れないということにもなりかねません。
そのため、ご自身で判断できない場合には、まずは弁護士に相談し、給付金の対象となる可能性があるかを案内してもらうのがおすすめです。
さらに弁護士に依頼すると、以下のようなメリットもあります。
難しい手続を任せられるため負担が減る
B型肝炎給付金を受け取る場合に、訴訟を起こすという手順を踏むことは避けられません。
しかし、「難しいことが多そう」、「裁判所に出向くのが大変そう」と感じる方もいらっしゃると思います。
弁護士に依頼すれば、訴状の作成など煩雑な手続を任せたり、あなたの代わりに裁判所へ出廷してもらったりできます。
時間的・精神的な負担も軽減され、スムーズに手続できる可能性が高まるはずです。
資料収集の代行・サポートをしてもらえる
アディーレなら、依頼者の方の負担となる書類の作成や裁判所への出廷はもちろん、資料収集の代行・サポートが可能です。
一部の資料については、ご自身で用意していただくことになりますが、以下のような資料は、原則としてアディーレの弁護士に収集を任せることができます。
- カルテなどの医療記録
- 戸籍・戸籍の附票
- 小学校の卒業証明書など満7歳になるまでに日本に居住していたことを示す資料
- B型肝炎ウイルスに感染していることを証明するための血液検査結果※
- 亡くなられたお母さまや年長のごきょうだいの血液検査結果※ など
※過去にこれらの血液検査を受けていることがある場合
また、依頼者の方ご自身で集める必要のある書類についても、収集方法についてのアドバイスや、見つからない場合には代替資料の提案をさせていただきますのでご安心ください。
【無料診断】B型肝炎の給付金をもらえる可能性をチェック!
「弁護士に相談するか迷っている」、「相談すべきかわからない」という方は、無料診断で給付金を受け取れる可能性があるかだけでも確認してみることをおすすめします。
この無料診断を使えば、3つのかんたんな質問に答えるだけで、B型肝炎の給付金を受け取れる可能性があるかわかります。
診断の結果、給付金を受け取れる可能性があるとわかれば、弁護士に相談するきっかけにもなるはずです。
診断は無料でできるので、少しでも心当たりのある方は、ぜひ確認してみてください。
まとめ
一次感染の方で、以下に当てはまるケースでは、B型肝炎の給付金を受け取ることができません。
- 感染原因が集団予防接種等ではない方
- 持続感染をしていない方
- 昭和16年7月1日以前または昭和63年1月28日以降に生まれた方
- 満7歳を迎えてから初めて集団予防接種等を受けた方
- ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している方
- 証拠となる資料がない方
ただし、二次感染者・三次感染者として給付金の受給対象となる場合もあります。
また、無症候性キャリアの方やご遺族の方も、要件を満たせば給付金を受け取れるため、ご自身で「給付金をもらえない」と決めつけてしまうことはおすすめできません。
給付金の対象かわからない場合には、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
アディーレなら、B型肝炎の給付金に関するご相談は何度でも無料です。
ご相談いただいた結果、給付金の対象ではなかったとしても費用は一切かかりませんので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士からのメッセージ
何の落ち度もない方々が、B型肝炎ウイルスに感染し、その本当の原因もわからずご本人やそのご家族が辛く苦しい思いをされてきました。その方々を救済するためにB型肝炎訴訟の制度ができました。おひとりで悩まず、気になることはどんなことでもお気軽にご相談ください。皆様の心の支えになれるよう、常にご依頼者様の立場になって考え、B型肝炎訴訟のお手続きをさせていただきます。